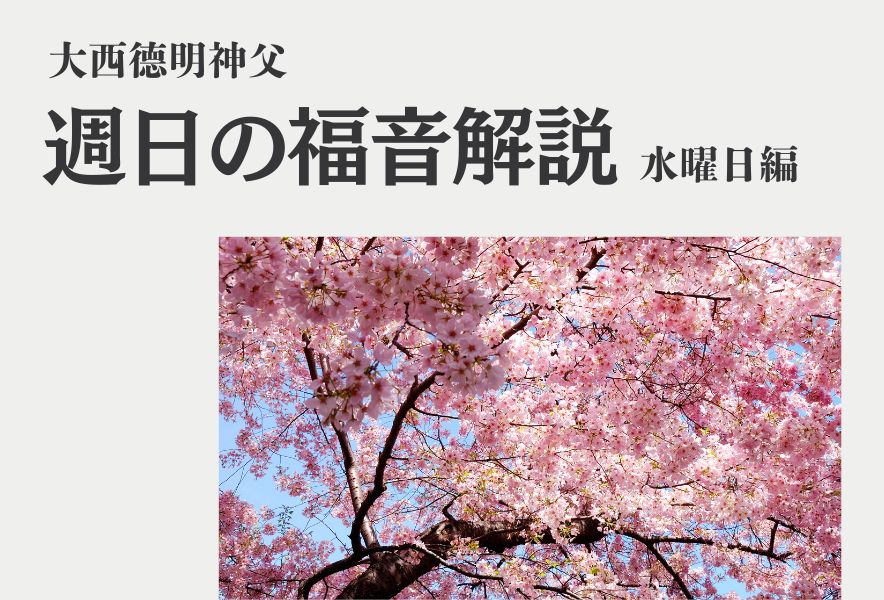マタイ5・17–19
14 その後、十二人の中のひとり、イスカリオテのユダという者が、祭司長たちの所に行って、 15 あの男をあなた方に引き渡せば、いったいいくらくれますか、と言った。すると、祭司長たちは銀貨三十枚を支払った。 16 その時から、ユダはイエスを引き渡す機会を窺っていた。
17 除酵祭の第一日、弟子たちがイエスの所に来て、あなたのために過越の食事をどこで用意しましょうか、と言うと、 18 イエスは言われた。「町のアノ人の所に行って、わたしの時が近づいた。わたしはあなたの家で弟子たちとともに過越の祭りを祝う、と先生がおっしゃっています、と言いなさい」。 19 弟子たちはイエスが命じられたとおりにして、過越の食事の用意をした。
20 夕方になると、イエスは十二人の弟子たちとともに食卓に着かれた。 21 一同が食事をしていると、イエスは言われた。「あなた方によく言っておく。あなた方の中のひとりがわたしを裏切ろうとしている」。 22 弟子たちは深く心を痛め、主よ、まさか私ではありませんでしょう、と口々に言い始めた。 23 イエスはお答えになった。「わたしと一緒に鉢に手を浸した者がわたしを裏切る。 24 まことに、人の子は自分について書かれているとおりに去っていく。しかし、人の子を裏切るその者は不幸である。その人はむしろ生まれなかったほうがよかったであろう」。 25 すると裏切り者のユダが口を挟んで、先生、まさか私ではありませんでしょう、と言うと、イエスは言われた。「そうだ」。
分析
マタイによる福音書26章14-25節は、イエスの受難の直前に起こった重要な出来事を描いています。イスカリオテのユダがイエスを祭司長たちに売り渡す決断をし、その後の過越の食事の席でイエスが裏切りを予告する場面です。この出来事は、神の救いの計画が人間の罪と裏切りをも含みながら成就していくことを示しています。
イスカリオテのユダは、銀貨三十枚でイエスを売り渡すことを祭司長たちと取り決めました。この「銀貨三十枚」という金額は、出エジプト記21:32において奴隷の命の値段として定められている金額と一致します。つまり、ユダはイエスを奴隷と同じ価値で売り渡したのです。これは、ユダがどれほどイエスを低く見ていたかを象徴するとともに、神の御子が人間の罪によって軽んじられ、犠牲として捧げられることを示唆しています。
その後、イエスと弟子たちは過越の食事の席につきます。過越祭は、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放されたことを記念する祭りであり、この食事の中でイエスは新しい「救い」の意味を示すことになります。しかし、その神聖な場面の中で、イエスは「あなた方の中のひとりがわたしを裏切ろうとしている」と宣言されました。この言葉は、弟子たちに衝撃を与え、「まさか私ではないでしょうか」と問いかける姿が描かれています。
イエスの答えは曖昧ではなく、「わたしと一緒に鉢に手を浸した者がわたしを裏切る」と明言されました。この表現は、単に食事を共にしているという事実を指すのではなく、最も親しい者の中から裏切りが生じることを強調しています。裏切りは敵からではなく、最も近い者から起こるという悲劇的な現実を示しているのです。
ユダが「先生、まさか私ではありませんでしょう」と問いかけたとき、イエスは「そうだ」と答えられました。この言葉には、ユダが自らの行為の責任を自覚し、選択していることを示唆する意味が込められています。イエスはユダの心を見抜きながらも、彼に悔い改めの機会を与えていたのです。
神学的ポイント
1. 神の救いの計画と人間の罪
イエスの受難は、神の計画の中で予見されていました。「人の子は自分について書かれているとおりに去っていく」というイエスの言葉は、メシアの苦難と死が聖書の預言に基づいていることを示しています。しかし、これはユダの裏切りが必然であったという意味ではなく、彼自身の自由意志による選択であったことが強調されています。
2. 銀貨三十枚の象徴性
ユダがイエスを売った銀貨三十枚という金額は、旧約聖書において奴隷の命の価値として定められていました。この出来事を通して、イエスが人間の罪のために「代価」として支払われる存在であることが示されます。これは、贖いの神学の核心に関わる重要なポイントです。
3. 裏切りの責任と選択
ユダの裏切りは、神の計画の中に組み込まれていましたが、それは決して「運命」によって定められたものではなく、ユダ自身の選択によるものでした。イエスはユダに対して、何度も悔い改めの機会を与えておられましたが、ユダはその招きに応じることなく、自らの道を選んでしまいました。
4. 共同体の中での裏切り
イエスを裏切ったのは外部の敵ではなく、十二弟子の一人でした。これは、裏切りが最も親しい関係の中で起こり得ることを示しています。この現実は、教会や信仰共同体においても適用される普遍的な問題です。私たちは互いに信頼し合う中で、どのように誠実さを保ち、神の愛に生きるかが問われています。
講話
この福音箇所は、単なる過去の歴史ではなく、私たち自身の心の中に問いを投げかけています。ユダの選択は、彼だけのものではなく、私たちもまた、日々の選択の中でイエスに対して忠実であるか、それとも彼を裏切る道を歩むかが問われています。
ユダは、イエスを知りながらも、自分の思い通りの救い主像に固執し、神の計画を受け入れることができませんでした。これは、私たちにも当てはまる課題です。私たちは、神が私たちに求める道を歩もうとしているのか、それとも自分の思い通りに物事を運ぼうとしているのか、改めて考えさせられます。
また、ユダはイエスを「先生」と呼びましたが、他の弟子たちは「主よ」と呼びました。この違いは、ユダの信仰のあり方を象徴しています。彼はイエスを尊敬はしていましたが、「主」として受け入れていなかったのです。私たちもまた、イエスを単なる偉大な教師としてではなく、人生の主として受け入れているでしょうか。
私たちの日常の中にも、裏切りの誘惑があります。それは、直接的な行動だけでなく、神への信頼を失うこと、信仰よりも世の価値観を優先すること、愛よりも自己中心的な考えを選ぶことなど、さまざまな形で現れます。しかし、イエスはユダに対しても最後まで機会を与えられたように、私たちにも悔い改めの道を示しておられます。
この福音を通して、私たち自身の信仰を省み、イエスに忠実であることを選び取る決意を新たにすることが求められています。神の愛と真理に生きる道を歩むために、私たちはどのような選択をするのか—それが今日の私たちへの問いかけです。