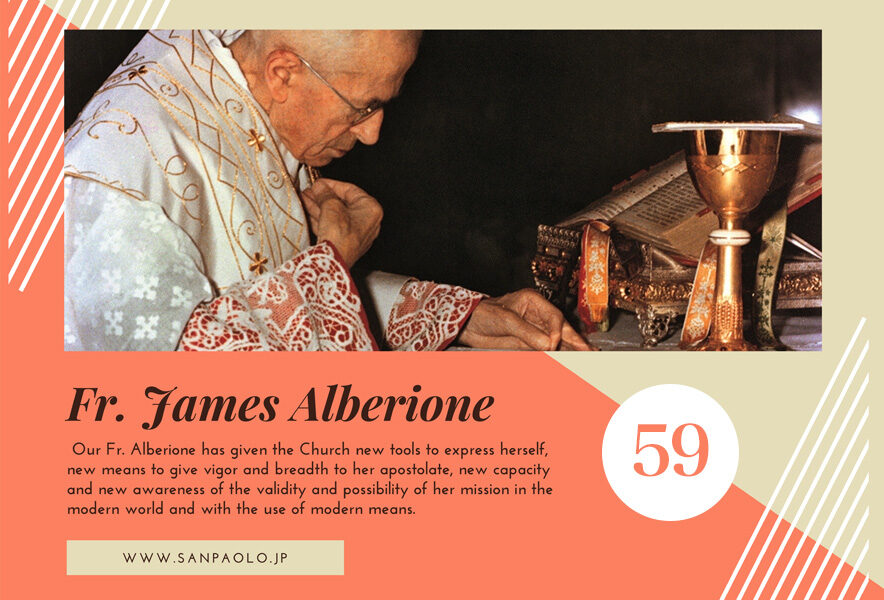一九三七年(昭和一一年)の暮れに、ローマの志願院で、一つの奇跡が起こった。ローマの冬は一般に温暖ですごしやすいが、その年の冬は、例外的に寒かった。それで志願者の中に流行性感冒が流行した。幾人かは気管支肺炎にまでなったので、この人たちを隔離せねばならなかった。しかし、志願院は、部屋が足りなくて病室らしいものはない。病人を一体どこに移せばよいのか。志願者の係りの神父も看護シスターも困っていた。
院長のアルベリオーネ神父の所へ相談に行くと、「それでは私の部屋を使いなさい」といって即座にあけてくれた。病人の中でも二人の志願者(その中の一人は現在のスペチアーレ神父)は、重態でもう助からないのではないか、奇跡を待つほかはないと医者からサジを投げられていた。
スペチアーレ神父の回想によると、同神父は、南イタリア生まれの南国育ち、寒さに弱く、アルバの志願院行きをアルベリオーネ神父に免除してもらい、ローマの志願院で四年前から修業を積んでいた。たまたま昭和一一年の寒い暮れに、志願院の近くを、仲間といっしょに、汗を流し、雨にぬれて散歩したのである。もともとひ弱な体であったので、たちまち、熱を出し、せき込んでしまった。今のように流行性感冒に効く抗生物質やワクチンがあるわけではない。暖かくして寝ているのが関の山、ちょうど主の御降誕祭も近づいていた。
アルベリオーネ神父は何回も病人を見舞って、その都度祝福を与えた。医者は重態の志願者を見て言うのだった。「幼な子がお生まれになるというのに、この小さな若者たちが死んで行くのを幼な子イエスはお許しになるだろうか?」と。しかし、アルベリオーネ神父は、確信ありげにこう言って、みんなを安心させるのであった。「幼な子イエスは、御降誕祭が、悲しいお通夜になることを許すはずがない」と。
そしてアルベリオーネ神父は、真夜中のミサを始める前に、病室となった自分の部屋に行き、「みなさんクリスマスおめでとう。病気がなおるように聖母マリアに熱心に祈ります」と言って慰めるのであった。御降誕のミサは三回できることになっているが、第一回目のミサのあと、アルベリオーネ神父は、付き添いの神学生に、病人の様子を見に行かせた。二人の病人には変わった所がなかった。
第二回目のミサのあとでの報告では、「少し病状がよくなっているみたい」とのことである。これに力をえてアルベリオーネ神父は引き続き第三回目のミサを終えて、感謝の祈りを何分かしたのち、神父は再び病人を見舞った。容態は本当によくなっていた。神父は長い間、だまって祈った。それから看護シスターに「よく看護しなさい」と頼んだのち、少し休みに行こうとして動き出した。しかし、どこに休みに行くあてがあったのだろうか? 夜中の二時が過ぎていた。外は雪がちらつき、身の凍るほどの寒さであった。
そのころ、志願院の別棟が建築中であった。しかし、そこには、いくつかの部屋は、あったものの、ドアも窓もないのでまだ人の住めるものではなかった。それでもアルベリオーネ神父は、建築資材の散らばった部屋の一つを片付け、毛布と仮りのマットを持ち込んで休んだのである。一時間少したってから、神父は再び、病室に姿を見せた。寒さにぶるぶるふるえ、顔はまっ青になりながらも、落ち着いてほほ笑みながら、病人たちの様子を見に来たのである。
シスターは、びっくりしてたずねた。「どうしてあなたは四時前にここにいらしてのですか?」と。神父は、落ち着いて、単純に答えた。「あの部屋はどうも寒くてね。眠れなかったよ。でもシスターは心配しないでよい。これから私があなたと交替してあげるから。休みに行きなさい。私はここにいるから。」こう言って神父は、部屋の中を足早に歩き回りながら、こごえたかじかんだ手足を暖めていた。
この記念すべき夜以来、若者の病状は、めきめきとよくなり、ついには全快してしまった。そのうちの一人、スペチアーレは、その三年後の一九四〇年(昭和一五年)に一八歳でパウロ会を退会し、高校、大学の課程を続けたが、アルベリオーネ神父とパウロ会の恩を忘れず、五年後の終戦の年に親の反対を押し切って再入会した。それには退会の際にアルベリオーネ神父の導きと励ましがあったのである。
「君はまだ若いから両親の言うことに従って、修道服を脱ぎ、世間に帰りなさい。勉強がよくできるようになり、召命もあると感じたら帰ってきなさい。神と人々の助けで君はそうなるだろう」と。神父が、彼の未来を読んだ通りになった。のちにスペチアーレは、司祭となってからずっとアルベリオーネ神父の亡くなるまで約二〇年間、その秘書として影のように付きそい、神父の手足のように働いた。
アルベリオーネ神父の取り次ぎによる病気回復は、ほかにもたくさんある。 気管支炎をわずらっていた一人のパウロ会の神父は熱を出して苦しんでいたが、一つの大黙想を終えると、すぐヴェンティミリア教区の司祭たちの黙想指導に出かけねばならなかった。その時、アルベリオーネ神父に、こう訴えた。「プリモ・マエストロ、どうしましょうか? 声が出ないのですが……」
「私といっしょに、台所のシスターのところに行って、熱い牛乳を茶わんに一杯のみましょう。」
しかし、例の神父は、牛乳を飲むと、どうしてもからだの具合が悪くなるので、二〇年来この方、牛乳は飲めなかったのである。アルベリオーネ神父は、相手が当惑しているのを見てとり、みずから相手を誘って台所へ入って行った。そして相手に牛乳を茶わん二杯も飲ませてから言った。「さあ、ヴェンティミリアに行きなさい。」この神父はすぐに出発し、何のさしさわりもなく任務をりっぱにやりとげたのである。
あるパウロ会の神父は、司祭たちの黙想会を指導するために、アルバノに行かなければならなかった。ちょうどその時病気になった。それでアルベリオーネ神父のところに同僚を遣わして「あの人は三八度の熱を出して休んでいます。どうしなければなりませんか?」と伝えた。すると神父は答えた。「安心して行きなさい。アルバノの湖畔の中に熱を投げ込みなさい。そうしたら、もう二度と、熱にとりつかれないから」と。その通りすると熱は下り、ゆだねられた任務を果たすことができた。
師イエズス修道女会のあるシスターは、長い間、腸をわずらい、急に熱が高くなることがあった。それでアルベリオーネ神父に面会した際に「ミサにあずかることもできないし、明日は聖母の祝日に歌うこともできません」と苦痛を訴えた。「ミサにあずかって歌うことはお好きなんでしょうね?」とアルベリオーネ神父は、そのシスターに念を押してから言った。「明日、よくなってらいいけれど。みましょう……」
翌日、その病人は熱が下がったので起き上がり、疲れも感ぜず、なんのさしさわりもなく、ミサにあずかり、ほかの人たちといっしょに、またソロで嬉しそうに歌った。
午後には、そのシスターは再び熱におかされ、がっかりしていた。その時、アルベリオーネ神父が姿を見せて、つぎのようにあっさり言うのだった。「私は病気回復をあなたに約束したのではありません。祝日に歌うことができればよいと言っただけです」と。
一九二六年パウロ会で働いていた師イエズス修道女会のシスターが鍋の中でたぎっていた湯で足に大やけどをした。数日後、シスターの容態はいっそう悪くなったが、その台所で働くかわりの者がいなかったので、アルベリオーネ神父は明日、台所に出て来て働きなさいと命令した。翌朝、そのシスターはベッドから起き上って、いつもの通り、台所で働いた。すると午後には足のやけどがすっかりなおっていたのである。
さてアルベリオーネ神父は、自分が決して健康に恵まれないにもかかわらず、神の恵みに信頼して、ほかの人の病気をなおしたばかりでなく、今度はより多くの霊的必要に応えて、また新しい修道女会を創立した。それは次に述べる善い牧者の修道女会である。
・池田敏雄『マスコミの先駆者アルベリオーネ神父』1978年
現代的に一部不適切と思われる表現がありますが、当時のオリジナリティーを尊重し発行時のまま掲載しております。