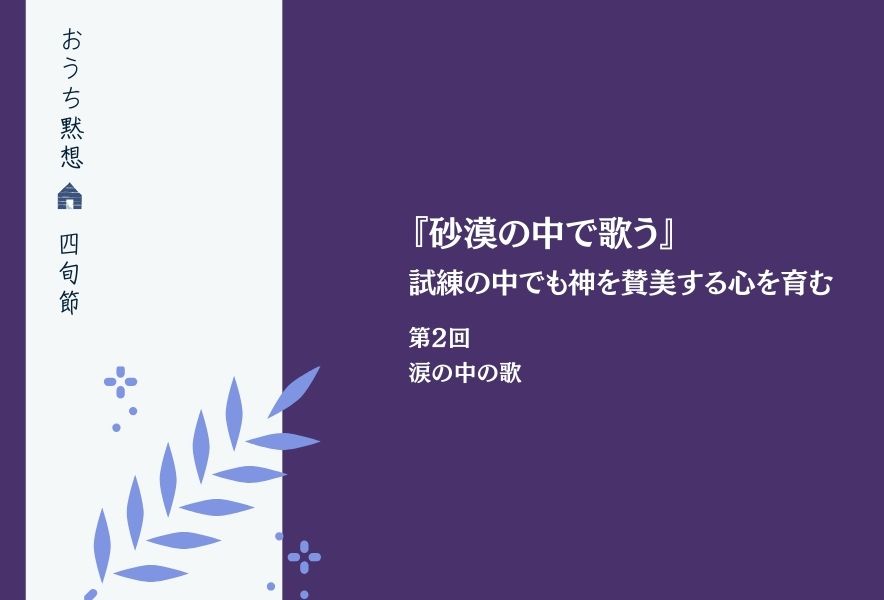―試練の中でも賛美を忘れない信仰―
詩編137編は「バビロンの川のほとりに座り、シオンを思って涙を流した。」という痛切な言葉から始まります。祖国を離れ、異国の地で捕囚状態となったイスラエルの民は、故郷のエルサレムを思い出して涙を流すしかありませんでした。かつての誇りやアイデンティティを根こそぎ奪われてしまった悲しみの中で、彼らは果たしてどのようにして神を賛美することができたのでしょうか。
バビロン捕囚と失われた歌
バビロンの捕囚はイスラエルの歴史において大きな転換点でした。神殿は破壊され、国は滅ぼされ、人々は散り散りにされるという悲劇的状況。彼らが「どうして異国の地で主の歌を歌えようか」と嘆いたのも当然のことです。信仰とは本来、神の臨在を感じやすい場所や状況で育まれるものだと考えがちですが、ここでは真逆の環境、つまり神の栄光を表す場所がすべて壊され、見通しもない最悪の状態が用意されていました。
しかし、その暗闇の中でさえ、彼らはシオン(エルサレム)を想い続けたのです。涙を流しながらも、故郷での祭りや神殿での礼拝の記憶を手放さなかった。この「想い続ける」という行為そのものが、すでに“賛美の種”であったといえるかもしれません。なぜなら、まったく希望がなければ想うことすら放棄してしまうからです。目の前の現実に押しつぶされそうになりながら、それでも心のどこかで「神が回復してくださるかもしれない」という一縷の望みを抱き続けること、それが嘆きと賛美を同時に抱える信仰の姿です。
涙が祈りに変わるプロセス
聖書に登場する多くの詩編がそうであるように、嘆きはしばしばそのまま祈りへと昇華していきます。私たちも人生の苦境で涙を流すとき、それを単なる感情の発散で終わらせるか、神への祈りへとつなげるかで大きな分かれ道が生まれるでしょう。詩編はしばしば「どうしてわたしをお見捨てになるのか」「敵を打ち砕いてください」といった激しい言葉も含みますが、その率直さこそが、神との生々しい対話を可能にしています。
泣くこと自体は恥ずかしい行為だと考えがちですが、聖書の世界では、嘆きや涙はむしろ神と繋がる“窓”とも言えます。隠していた本心をさらけ出すことで、偽りのない関係が生まれ、そこに神の慰めや導きが流れ込んでくるのです。バビロンに連行された民も、涙を流さざるを得ないほどの悲しみがあったからこそ、その悲しみを通して神に心を注ぎ出すことができたのではないでしょうか。
涙と賛美が両立する信仰
聖書の中には、嘆きと賛美がまるで相反する要素のように見えながら、実際には同時に存在する例が数多くあります。ヨブは財産や家族、健康までも奪われながらも神を呪わず、「主は与え、主は取りたもう。主の御名はほむべきかな」と告白しました。これは決して強がりや美化ではなく、心底打ちのめされた現実の中で、それでも神の主権を信じ続けるという姿勢です。
私たちの日常でも、深い悲しみのただ中で「神よ、あなたを賛美します」と口にするのは容易ではありません。しかし、まさにその困難さの中に信仰の真価が問われるのです。感情がついてこなくても、あえて神への感謝や賛美を言葉にすることが、絶望の闇に光を差し込むきっかけとなるかもしれません。バビロン捕囚の民が一見歌えない状況でありながら、心の奥底に神への帰属意識を失わなかったように、私たちも苦難の只中で神を忘れないという態度を選べるでしょう。
「歌を失う」経験の意味
人は痛みが大きすぎるとき、まるで声が出なくなるかのように「歌」を失ってしまうことがあります。それは突然の不幸、病、愛する人の死別など、人生の暗い谷間を通るときです。そのとき私たちは、「もう自分には歌う力がない」「祈ることさえできない」と感じるかもしれません。実際、悲しみが深いほど、言葉や声は届かない場所へと沈んでいくように思えます。
しかし、聖書が教えるのは、「歌えない」と感じる深淵にあっても、神は私たちの沈黙の叫びを聞き取っておられるということです。口から出る声でなくても、魂の奥底からのうめきがすでに神への祈りとなるのです。バビロンで涙を流した民のそばにも、神は見捨てることなく共にいてくださった。その事実に目を向けるとき、私たちの中に微かな“再び歌い始める”力が湧いてくるかもしれません。
涙から生まれる新しい賛美
やがてイスラエルの民は捕囚から解放され、再びエルサレムに戻ってきます。そして神殿を再建し、新たな礼拝をスタートさせました。そこには、かつての栄光をそのまま再現することはできないかもしれないという限界もあったでしょう。それでも、涙を通過した者たちの賛美は、以前よりもさらに深い意味を帯びていたはずです。自分たちの罪や弱さを認め、同時に神の憐れみと回復の力を知った者の歌は、ただ単なる“感情的な盛り上がり”ではなく、神の真実さを証しする力強い宣言となるのです。
涙は私たちの弱さを象徴するようですが、神の目には、その弱さのなかにこそ本物の賛美が生まれる土壌があるのかもしれません。悲しみを体験した者は、他者の痛みに寄り添う感性もまた育まれます。そうして生まれた賛美は、自分だけのためでなく、他者をも包み込む優しさと共感を帯びるようになるのです。
私たちが人生の暗い時を迎え、「もう歌など歌えない」と思わざるを得ない状況に直面したときこそ、詩編の嘆きの言葉や、バビロンの川辺で泣く民の姿に思いを重ねてみたいものです。そこには「涙の中でも神を見つめる姿勢」が貫かれており、やがては新しい歌へと続く道筋が用意されているのだと信じさせてくれます。